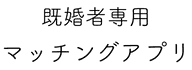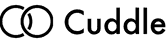%20(1).jpeg)
家族で食卓を囲む大切さ
2022.12.14家族が揃って食事をすることは、たくさんのメリットがあります。
とは言え、現代の家庭では、親の仕事の都合や、子供の年齢によっては習い事のスケージュールが詰まっているなどの理由で、家族揃って食事をすることが難しいかもしれません。
今回は、家族で食卓を囲む大切さについて考えてみましょう。
多様化するライフスタイル
最近、生活スタイルも多様化されて、家族がいても皆それぞれの時間で忙しく動いているため、孤食が多くなってきました。
孤食とは、一人で食事を食べることです。
大人が自分の意志で、一人で食べることを意味するのとは少し違います。
孤食は問題になっており、本当は家族と一緒に食事をしたいのにできない状態です。
親は家の中にいるのに用事などで忙しく、子供を一人食卓に座らせて食事をさせることも孤食に含まれます。
また、家族揃って食事をしていても、親がずっとスマホを扱っていて会話がないという家庭も増えています。
せっかく一緒に食事をしていても、これでは子供を放置していることと同様で、孤食になります。
厚生労働省による全国家庭児童調査(平成21年度)では、1週間のうち家族そろって一緒に夕食を食べる日数は「2~3日(36.2%)」が最も多く、朝食にいたっては「ほとんどない(32.0%)」が最も多いという結果が出ています。
その背景としては、核家族や共働き家庭の増加、また子供自身も塾や習い事で忙しく、家族のスケジュールがバラバラになっていることが挙げられます。
もちろん、誰でも家族一緒に食事をする回数を増やしたいと考えているはずですが、現状では、社会全体で構造を抜本的に見直す必要があるため、改善は難しいとされています。
このように現代の孤食問題は根が深く、家庭で大きな悩みのタネになっているのです。
食事バランスを良いものにしてくれる
一緒に食事をする相手がいれば、テーブルに並ぶ品数や、食材の種類は自然に増えるでしょう。
一人で食べるときは、自分の好きなものだけ食べて簡単に済ませてしまいがちです。
料理を作る側も、一人よりたくさん食べる人がいれば、いろいろな料理を作る気力もパワーも出てくるものです。
家族で食べた方が、自然に食事の栄養バランスを良いものにしてくれ、食べ過ぎなどの体調管理にも目が届きやすくなります。
心にも大きく影響する
食事の時間は、家族が集まり向きあって食卓を囲む時間になります。
毎日生活をしていて、こういったコミュニケーションの時間は他にはあまりありません。
また、時間があっても面と向かって話せなかったことが、食事を共にすることで自然にできるという場合もあります。
コミュニケーション以外にも、家族との繋がり・表現力・問題解決などが改善していることから、食事は精神的な面と切り離せないものだとわかります。
家族で一緒に食事をすることは、家族のコミュニケーションを深めるための大事な方法のひとつと言えるでしょう。
家族の食事時間はもっと増やせる
食べ物からの栄養的なことはもちろん、家族の機能を果たすための大切な要素があることがわかります。
夫が仕事で遅かったり、子供の習い事があったり、朝は起きる時間がバラバラで朝食時間が違ったりなど、なかなか家族みんなで食事をすることは難しいかもしれません。
しかし、なるべく家族との食事時間を大切にしようと心掛けることはできます。
週末だけは、家族揃って食べるとか、時間を合わせることができる人だけは一緒に食べるなど、それぞれが意識していけば、大切な家族と過ごす時間をもっと増やせるはずです。
終わりに
家族で揃って食卓を囲むということは、家族の繋がりを深めることができる上に、経済面にとっても驚くほどのメリットがたくさんあるのです。
食事をしながら会話をすると、子供も素直な心を開いて話してくれます。
どんなに忙しくても、この時間だけは確保できるように調整して、家族皆で楽しめるようにしましょう。
他のコラム
別居婚のメリット・デメリット こちら
他のコラムを読む
Related Articles.jpeg)
日本におけるジェンダーロールの変遷と現代の結婚観
.png)
会員数70万人突破!既婚者マッチングアプリ「カドル(Cuddle)」の口コミ・評判を徹底解説
.jpeg)
既婚者の女性の司法書士と出会う方法とは?