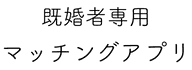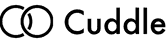%20(1).jpeg)
【既婚女性編】子供が産まれて変わったこと
2025.03.14子どもが生まれると生活が一変する――。これは多くのママが口にします。日本においても、結婚後に第一子が誕生した女性の多くが、日々のライフスタイルから金銭感覚、夫婦関係、住環境、キャリアまで様々な変化を経験します。ある調査では、子どもの誕生によって「時間の使い方」や「お金の使い方」が最も大きく変わった項目だと報告されており、かつて自分のために使っていた時間やお金の大半を子どものために費やすようになったという声が多く寄せられました。本記事では、日本の文化や制度を踏まえ、公式統計やインターネット上の調査データをもとに、「子供が産まれて変わったこと」の一般的な傾向をまとめます。
ライフスタイルの変化
まず日々の生活リズムやライフスタイルの変化です。赤ちゃん中心の生活となり、自分たち夫婦のために使える時間が大幅に減ったと感じる親御さんが非常に多くいます。例えば夫婦共通の趣味の時間や、二人で外出する機会が減り、「子ども中心の生活になった」と実感する声が目立ちます。実際、小さな子ども連れでの外出先は授乳室やベビーカー対応といった条件で限られるため、「行ける場所が減った」と感じるケースも少なくありません。
また、夜間の授乳やお世話による睡眠不足も深刻です。ある調査によれば、産後の母親の約3人に1人が「1日5時間未満」しか眠れていない状況だという結果が出ています。一方で、子どもが生まれたことで実家の両親(祖父母)との交流が増える家庭もあります。孫の顔を見せるために実家に帰省する頻度が上がったり、育児サポートを得るため親族とのつながりが深まるのは、日本ではよく見られる変化です。
お金の使い方
次に家計やお金の使い方の変化です。子育てには想像以上にお金がかかるものです。内閣府の調査によれば、第一子が生まれた直後(0歳児)に必要となる養育費は平均で年間約93万円にも上るとされています。月々のベースで見ても、乳幼児のいる家庭では「子どものために毎月数万円の出費増加」は避けられないようです。あるアンケートでは、5歳以下の子どもがいる家庭で「子ども関連の支出が毎月1万~5万円程度増えた」という回答がボリュームゾーンを占めています。特に食費の増加傾向が顕著で、子どもの栄養を考えて食材を選ぶようになることで食費が月1~3万円程度かさむ家庭が多いといいます。そのほか、オムツやミルクなどの生活雑貨費、子どもの衣服代なども数千円~数万円の範囲で出費が発生し、将来の教育費の積立を毎月行う家庭もあります。
こうした子育て費用の増加に伴い、今まで夫婦が趣味や娯楽に使っていた支出は削られがちです。実際、「趣味」や「外食」にかけるお金が大幅に減ったと感じる親が多く、子ども優先の家計になるにつれて「自分のための出費を我慢するようになった」という声も聞かれます。ただし、半数以上の親はそれを「苦ではない」と捉えており、我が子のためにお金の使い方が変わるのは当然だと受け止める人が多いようです。
夫婦関係
子どもの誕生は夫婦関係にも影響を与えます。日本では近年、出産後に夫婦仲が悪化する「産後クライシス」が注目されています。ある調査では、出産後に約3組に1組の夫婦が愛情の冷え込みを経験したと報告されています。特に妻(母親)の立場からは、「自分の生活は激変したのに夫は何も変わらない」という不満や、寝不足の中で家事育児を手伝ってくれない夫へのストレスなどが原因として挙げられています。こうしたすれ違いから、「子ども中心の生活になって夫婦の会話が減った」というケースも見られます。
もちろん、子育てを通じて協力し合うことで「パートナーへの信頼が深まった」と感じる夫婦もいますが、そのようなポジティブな変化を挙げる声は決して多くはありません。むしろ多くの夫婦では、良くも悪くも関係性が「恋人同士」から「家族」へと様変わりしたと感じるようです。別の調査では「夫婦仲が良い家庭ほど夫の家事・育児分担率が高い」というデータも報告されており、産後の夫の積極的な育児参加が関係改善のカギと指摘されています。
住まい
子どもが生まれることで、住環境や住まいに対する考え方にも変化が生じます。手狭なアパートからより広い住居へ引っ越しを検討したり、子育てに適した環境を求めて住む場所を見直す夫婦も少なくありません。実際、住宅取得に関するデータを見ると、第一子が誕生してから小学校入学前(0~5歳)のあいだにマイホームを購入したという世帯が全体の6割以上を占めています。このように、子どもが生まれたことをきっかけに「そろそろ持ち家を買おう」「郊外の子育てしやすい地域に移り住もう」と決断する家庭は多いのです。
また、引っ越しをしない場合でも、自宅の中で子ども部屋を準備したり、乳幼児が安全に過ごせるよう家具の配置や収納を見直すなど、住空間の工夫をする家庭も増えます。日本では、祖父母と同居する三世代世帯は以前ほど多くありませんが、里帰り出産で一時的に実家に滞在したり、両親が近くに住んでサポートするケースも見られます。いずれにせよ、子育てを機に「家」や「暮らしの場」に求める条件が変わるのは自然な傾向と言えるでしょう。
キャリア
キャリア(仕事)の面でも大きな変化があります。従来、日本では出産を機に女性が仕事を辞める例が多く見られ、「M字カーブ」と呼ばれるように女性の就業率は出産・育児期に一度低下する傾向がありました。しかし近年は制度整備の進展もあり、出産後も働き続ける女性が増えています。実際、第1子出産後も仕事を続けている女性は全体の約7割にのぼり、出産を機に退職する女性は約3割というデータがあります。また、厚生労働省の統計では女性の育児休業取得率は約90%に達しており、多くの女性が産休・育休制度を利用して職場復帰を果たしていることがわかります。
とはいえ、育児と仕事の両立は容易ではありません。育休から復帰した後、「以前のようにバリバリ働けない」「キャリアやポジションの維持が難しい」と感じる女性も少なくなく、ある調査では育休復帰後に8割近くの女性が何らかのキャリア上の壁を実感したとされています。時短勤務や在宅勤務など柔軟な働き方を選択する人もいますが、保育園の送迎や子どもの体調不良による急な欠勤など、子育て期特有の制約がキャリアに影響する場面も多々あります。一方で、企業側でも育児と仕事を両立しやすくするための支援策(在宅勤務制度の導入や育児中の社員への配慮など)が進みつつあり、男性の育休取得促進など家庭内外で女性をサポートする動きも広がっています。出産後のキャリア継続については、日本社会全体で試行錯誤しながら改善が図られている途上と言えるでしょう。
結論
以上のように、日本における既婚女性は、子どもが生まれたことによって生活のあらゆる面で大きな変化を経験します。日々の過ごし方や優先順位は子ども中心となり、家計の配分や夫婦の関係性にも変化が及びます。住まいについても、子育てしやすい環境を求めて住居を変えたり工夫を凝らすようになりますし、仕事との両立という新たな課題にも直面します。
ただ、これらの変化は決してネガティブなものばかりではありません。子どもの存在は大変さと同時に喜びももたらし、それまで気づかなかった価値観の変化や成長の機会を与えてくれます。日本では行政の子育て支援策や育休制度の整備が進みつつあり、TwitterやInstagramなどのSNSやママ向けコミュニティでも子育ての悩みや喜びを共有し合う動きが広がっています。こうした社会のサポートや家族・周囲の協力を得ながら、子どもが生まれた後の新しい生活に適応していくことが、親となった女性に共通する歩みと言えるでしょう。
他のコラムを読む
Related Articles.png)
会員数70万人突破!既婚者マッチングアプリ「カドル(Cuddle)」の口コミ・評判を徹底解説
.jpeg)
既婚者の女性の司法書士と出会う方法とは?
.jpeg)
既婚者女性の公認会計士と出会う方法とは?