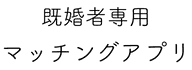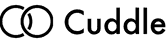.jpeg)
江戸時代の結婚と恋愛事情をひもとく
2025.03.31江戸時代の結婚制度と夫婦のカタチ、恋愛観をわかりやすく解説。遊女や妾など町人文化・武家社会の恋愛事情をひもとき、現代との共通点も探ります。
江戸時代の夫婦って恋愛していたの? 現代の結婚観とはかなり違うと聞くけれど、本当のところどうだったのでしょうか。実は、江戸時代の結婚制度では「結婚」と「恋愛」が今よりずっとハッキリ分けられていました。今回は、江戸時代の結婚制度や夫婦観、当時の恋愛観の特徴をわかりやすくひもときながら、遊女や妾(めかけ)といった文化も交えてご紹介します。そして最後に、現代との比較を通して、今も昔も変わらない人間の心のつながりへの思いについて考えてみましょう。カジュアルな語り口でお送りしますので、歴史が苦手な方もぜひ気軽にお読みください。
江戸時代の結婚制度と夫婦観
江戸時代、結婚は家と家の結びつきという現実的な目的が最優先でした。多くの場合、親同士や仲人によって決められるお見合い結婚が一般的で、本人たちの恋愛感情は二の次だったのです。たとえば武士や裕福な町人(商人)階級では、似た身分・家柄の間で縁組みするのが当たり前でした。「誰と結婚するか」は男女本人よりも親の意思が重視されたイベントだったのです。お見合い自体は江戸時代にも存在しましたが、現代のような自由な出会いの場というより、最終確認のための儀式に近かったようです。こうした背景には、当時の日本社会で支配的だった家父長制や儒教の価値観があります。武家社会では妻は夫に従うものとされ、「三従の教え」(幼少期は父に、嫁しては夫に、老いては子に従う)など女性の従属を説く倫理観がありました。しかしそれはあくまで理念上の話。実際の庶民生活では、夫婦は現実的なパートナーとして協力する関係でもあったのです。
家を継ぐための結婚
江戸時代の結婚は基本的に家制度の中で位置づけられていました。武士階級では藩や主家の許可も必要で、結婚は家同士の政略的な意味合いも帯びていました。一方、庶民(農民や町人)にとっても結婚は家の存続・生活の安定が最優先。江戸時代には「嫁入り・婿入り」という言葉の通り、一方の家に配偶者が入る形を取り、新たな所帯を構えるわけではありませんでした。とくに庶民の場合、正式な婚姻届のような制度も武家を除けば存在せず、かなり緩やかな結婚の形だったようです。例えば農村では、結婚前に男性が女性の実家に通う「婿入り婚」という事実婚スタイルが一般的でした。一定期間そうした関係を続け、女性側の家で同居した後、改めて妻が夫の家に「嫁入り」するという流れです。これは嫁がいきなり姑に仕えるのではなく、夫婦がお互いを知り生活に慣れる期間でもありました。また農家では女性が家業を支える貴重な働き手だったため、「お試し期間」を経て本格的に嫁として迎える合理的な風習だったのです。そのため婚前交渉も珍しくなく、子どもができてから正式に嫁入りするケースも多かったとか。現代で言う“できちゃった婚”も当時はごく当たり前で、むしろ子宝に恵まれることは喜ばしいことだったんですね。
恋愛は二の次?当時の「恋愛観」
こうした江戸時代の結婚では、恋愛感情だけを理由に結婚するケースは少なかったようです。そもそも「恋愛」という言葉自体、明治期に生まれた新しい言葉で、江戸時代には「色恋」と表現されていました。現代のように恋に憧れる人は「浮気者」あるいは「艶気者(つやけもの)」なんて呼ばれたそうです。好き合っているから結婚する、という発想は当時の常識からするとむしろフシギで、恋愛だけで結婚することは「浮気結婚」なんて揶揄(やゆ)されてもいました。要するに江戸時代、人々にとって結婚は生活の手段であり、恋愛は娯楽の一種という位置づけだったのです。「好きだから一緒になる」ではなく、「家を継ぐため・働き手を得るために一緒になる」というのが一般的な結婚観でした。当時はまだ恋愛結婚は珍しく、身分の高い人からは「恋愛結婚なんて下層の者がするもの」と見なされていたという指摘もあります。もっとも、夫婦の間にまったく情愛がなかったかというと、そうとも限りません。長年連れ添えば愛情や信頼も芽生えるでしょうし、仲睦まじい夫婦も当然いたでしょう。ただ少なくとも結婚のスタート地点でロマンチックな恋愛感情は重要視されていなかった、という点が現代との大きな違いです。
庶民の恋愛事情:町人文化が育んだ“粋”
形式ばった結婚と切り離されていたとはいえ、人間ですから恋愛(色恋)そのものは江戸の人々も楽しみました。特に都市の町人文化において、恋や情緒を楽しむ風潮は豊かでした。江戸の町人たちは経済的にも徐々に豊かになり、娯楽や文化が花開きます。その中で、生身の恋愛を描いた浮世草子や人形浄瑠璃・歌舞伎の世話物(恋愛劇)が大人気となりました。作家井原西鶴は『好色一代男』で遊里での遊興に生きる男を描き、近松門左衛門は町人の不倫や心中(駆け落ち)をテーマにした名作を次々と世に送り出しました。観客はそうした恋愛物語に熱狂し、「色恋」に心をときめかせたのです。
吉原遊郭と“浮気”の文化
江戸の町人男性にとって、吉原遊郭は切っても切れない存在でした。吉原は幕府公認の大型遊女街で、多くの遊女(ゆうじょ)たちが客を取っていました。男性たちは吉原で美しい遊女たちと遊び、飲めや歌えの大騒ぎをしたものです。ここで言う「遊ぶ」とは単なる色欲を満たすだけでなく、ロマンスを擬似体験するような面もありました。上等な花魁(おいらん)ともなれば教養もあり、客との間で和歌をやりとりしたり、まるで恋人同士のような情緒的やり取りを楽しんだと言います。「旦那」となった馴染み客が遊女を身請けして妻同然に囲うこともあり、庶民男性にとって遊女はある意味“セカンドパートナー”的な存在でもあったでしょう。もっとも、遊郭はあくまで男性客のためのもので、既婚女性が恋愛を楽しむ場ではありませんでした。当時の法では妻の不倫(不義密通)は重罪で、露見すれば妻も相手の男も死罪に処せられかねない厳しいものでした。とはいえ実際には「よくあること」でもあり、バレた場合も多くは示談金(慰謝料)で解決されていたようです。一方、夫の浮気(既婚男性が未婚女性と関係を持つ)は法律上は咎められず黙認されていました。当時の常識では「男は外で遊ぶもの、女はそれを内で支えるもの」というダブルスタンダードがあったのですね。
離婚と再婚は意外と自由?
夫に浮気されるだけでなく、我慢ならなければ別れるという選択も江戸の妻たちは持っていました。実は江戸時代、現代より離婚が盛んだった一面もあります。江戸後期には離婚率がおよそ4.8%に達し、なんと2010年代日本の約1.8%を遥かに上回っていました。当時の離婚は「駆け込み寺」よりも仲人などの話し合いで円満に離縁するケースが多かったようです。離婚の際、夫から妻に渡される「三行半(みくだりはん)」と呼ばれる離縁状には「あなたが誰と縁づこうとも一切異存はありません」といった文言が記されており、これはつまり「あなたは自由に再婚していいですよ」という再婚許可証の役割を果たしました。実際、離婚した女性の約35%が新たなパートナーと再婚していたという村の記録もあります。現代と比べると、江戸の庶民女性は「離婚→再婚」へのハードルが低かったのです。このように町人文化では、結婚に縛られすぎず男女が柔軟に関係を結び直すこともできました。それだけに、夫婦以外の異性との“恋”も身近なものだったと言えます。「浮気」はダメとされながらも、実際には吉原のような発散の場があったり、離縁というリセットも効いたりと、現代よりある意味おおらかだった側面もあるのですね。
武家社会の恋愛事情:武士と側室・妾制度
では武士階級ではどうだったのでしょうか。武家の正式な結婚(正室)は家の結束のための政略要素が強く、愛情より「家柄」「石高(収入)」が重んじられました。しかし武士も人の子、夫婦以外の恋とは無縁ではありません。特に子孫を残す必要がある家では、正妻に子どもができない場合などに側室(妾)を持つことが公然と認められていました。大名や旗本クラスの武士は正妻のほか複数の側室を抱える場合もあり、正室の産んだ子が「嫡子」とされる一方で、側室の子も公認され家督争いになることさえありました。側室・妾というと聞こえが悪いですが、これも当時としては家を存続させるための合理策です。「浮気」というよりもう一人の妻を持つ感覚に近く、現代で言うところの“二人目のパートナー”ですね。側室を持てるのは主に上流武士でしたが、裕福な商人なども妾を囲うことがありました。例えば江戸の豪商紀伊國屋文左衛門は複数の妾を持っていたと言われますし、徳川将軍の大奥などは正妻と御台所に加え多数の側室が暮らす巨大ハーレムでした。一方、武家の女性が夫以外の男性と関係を持つことは固く禁じられました。先述の通り、既婚女性の不倫は「不義密通」と呼ばれる重罪で、武士の家では家名断絶につながりかねない大問題です。現行犯であれば夫が妻と間男をその場で斬り捨てても「武士の面目を立てた」として罪に問われなかったほどです。極端な例ではありますが、それだけ武家社会では妻の貞操が家の名誉とみなされていたのです。もっとも、だからといって武士の妻たちが皆恋愛感情を押し殺していたかというと、人間ですからそうでもありません。中には叶わぬ恋に身を焦がし、悲劇の末に名を残した例もあります。歌舞伎や浄瑠璃の世界では武家の不倫物語も描かれています。例えば近松門左衛門の『大経師昔暦(だいきょうじむかしごよみ)』では武家の人妻おさんと手代茂兵衛の不義が露見し、茂兵衛が処刑される悲劇が描かれました。江戸の世でも「道ならぬ恋」は存在し、命がけのドラマとなり得たのです。
文学・浮世絵に見る江戸の恋愛模様
江戸時代の恋愛事情を語る上で、文学作品や浮世絵に残された当時の空気感は貴重な手がかりです。庶民の恋愛はしばしば創作のテーマとなり、人々はそれらを通じて恋の機微に共感しました。ここでは有名な作品や人物のエピソードから、江戸の人々がどんな恋愛観を持っていたのか探ってみましょう。
恋に殉じる?近松門左衛門の描いた純愛
江戸中期の劇作家近松門左衛門は、当時実際に起きた男女の情死事件をもとに『曾根崎心中』『心中天網島』などの浄瑠璃・歌舞伎作品を書き上げ、大ヒットさせました。近松の世話浄瑠璃には、許されぬ恋に苦しみ抜いた末に心中(=情死)してしまう男女がたびたび登場します。例えば『曾根崎心中』では、お初と徳兵衛という若い恋人同士が周囲に引き裂かれ、最後は「この世で結ばれないなら来世で」と抱き合って命を絶ちます。現代から見るとショッキングですが、当時の観客はこの悲劇にむしろロマンを感じ、「恋の手本」と称える者までいたとか。それほどまでに、純粋な恋に殉じる物語は人々の胸を打ったのです。近松作品の背景には、「経済的には豊かになっても身分制度に縛られて生きる町人の鬱屈(うっくつ)」がありました。愛し合う二人が社会のしがらみに阻まれるという構図は、江戸庶民にとって身近でリアルな問題だったのでしょう。だからこそ「心中もの」は大いに支持され、“叶わぬ恋は死で貫く”という極端な美学さえ肯定的に受け取られたのかもしれません。もちろん実際に心中する人ばかりではありませんが、「恋に命を賭ける」気概が称賛されるあたり、当時の人々の恋愛観が垣間見えます。
滝沢馬琴の意外な一面:遊郭通いと批判
勧善懲悪の大作小説『南総里見八犬伝』で有名な滝沢馬琴(曲亭馬琴)も、実は若い頃は恋愛沙汰で波乱がありました。馬琴は真面目な文化人のイメージですが、20代の頃に失意のあまり吉原の遊郭に通い詰め、性病(梅毒)に罹ってしまったと日記に綴っています。なんとも人間くさいエピソードですが、彼はその後、親から勧められた縁談で悩みました。相手は吉原で店を営む家の娘さん。馬琴は「遊郭は人身売買の巣窟だ」と日記に書いており、そのような家の娘と結婚するのは嫌だと断ったのです。遊郭に通って散々お世話になったにもかかわらず、いざ妻とするとなると尻込みする──このあたりに、当時の男性の本音と建前が見えてきます。つまり「遊女は遊び、妻は別」という割り切りです。馬琴ほどの人物でも恋と欲には勝てず遊蕩しましたが、妻にする女性の出自にはこだわった。このエピソードは、江戸時代の男性たちが婚外の恋愛(色恋)と正式な結婚相手をしっかり線引きしていたことを物語っています。
与謝野晶子の大恋愛:明治に花開く恋愛結婚
江戸時代の価値観が明治以降どう変わっていったかを象徴する人物として、歌人の与謝野晶子を挙げてみましょう。晶子は明治~大正期に情熱的な恋の歌を数多く残した女性です。彼女自身の恋愛もドラマチックでした。与謝野晶子は与謝野鉄幹(与謝野寛)という歌人グループ主宰者に弟子入りし、やがて鉄幹と不倫関係になります。当時鉄幹は妻・滝野がいましたが、晶子の才能と情熱に惚れ込んだ鉄幹は妻と離婚し、晶子を正式に妻に迎えました。明治33年(1900年)のことです。周囲は大騒ぎしましたが、二人は愛を貫き、以後晶子は夫とともに短歌誌『明星』を主宰しつつ13人もの子供を産み育てました。晶子の生き方は「恋愛結婚」の先駆けと言えるでしょう。
この与謝野鉄幹・晶子夫妻の例は、明治以降の結婚観の変化を如実に示しています。江戸時代には考えられなかった「妻子ある男性が妻と別れて愛人と再婚する」などという選択が現実に起き、それが文学作品にも負けないロマンとして語られたのです。晶子は世間の非難にも負けず情熱的に愛を歌い、「その子二十 櫛にながるる黒髪の おごりの春の 美しきかな(みだれ髪)」など大胆な恋の歌を発表して当時の女性たちを驚かせました。彼女の生き様は、封建的なしがらみから個人の恋愛感情を解放する時代の到来を象徴しています。
今と昔、変わらぬもの:心のつながりを求めて
こうして見てくると、江戸時代の結婚は現代とはかなり様相が異なっていました。制度的にも一夫一妻の形をとりつつ実態は緩やかで、経済的・家制度的な理由が重視された結婚。恋愛は公式には結婚と切り離され、夫婦以外での“心のつながり”を男女ともに求める余地があった社会──それが江戸時代だったと言えます。では現代はどうでしょうか。現代日本では明治以降に法律上も一夫一妻制が確立し、恋愛結婚が当たり前になりました。パートナー選びは自由で、本人の愛情が最重視されます。しかしその一方で、結婚後にパートナー以外の人に心惹かれてしまうケースは後を絶ちません。不倫や婚外恋愛の話題がニュースやワイドショーを賑わせることもしばしばですよね。法律的・倫理的には「不貞はいけない」とされる令和の世ですが、そこで悩む人々がいるのも事実です。最近では配偶者以外に心の安らぎを求める相手を持つ人を指して「セカンドパートナー」なる言葉も生まれました。結婚という制度の形こそ変われど、人がより深い心のつながりを求める気持ちは今も昔も変わらないのかもしれません。江戸時代の人々は、形式的な夫婦関係の外に恋や情を見出しました。それは現代に生きる私たちにも通じる感覚ではないでしょうか。もちろん、だからといって「浮気推奨!」ということではありませんよ! ただ、江戸の夫婦たちもまた人知れず悩んだり迷ったりしながら、それでも自分にとっての幸せな心のつながりを模索していた──そう考えると、なんだか400年の時を超えて人間臭さに共感できますよね。歴史の中の夫婦像を知ることで、今の自分たちの夫婦関係やパートナーシップについて改めて考えるヒントになるかもしれません。江戸の昔も令和の今も、結局大事なのはお互いを思いやる気持ちと絆。形は違えど、人が誰かと心を通わせたいと願う気持ちは普遍なのでしょう。
他のコラムを読む
Related Articles%20(1).jpeg)
効果的な謝罪の科学:上手な謝り方がもたらす人間関係の変化
.jpeg)
日本におけるジェンダーロールの変遷と現代の結婚観
.png)
会員数70万人突破!既婚者マッチングアプリ「カドル(Cuddle)」の口コミ・評判を徹底解説